批評家というメディア:現代における批評活動について考える
批評家というメディア
今日において、批評活動を始めるにあたり、まず問われるのは「どのような手段を選ぶか」だ。オンラインかオフラインか。文章か映像か音声か。単発か継続か。これらの選択は、今や活動の前提であり、批評という営みをどこでどう展開するのかという戦略に直結する。
かつては、雑誌や出版社、美術館、大学といった「場」から依頼を受けることで批評活動は成り立っていた。だが今日では、批評家自身が企画を立て、発信の場を自らつくることが可能だ。つまり、批評家は自ら「メディア」になることができるようになった。
この「個人のメディア化」は、オールドメディアの衰退とも関係しており、プロフェッショナルな環境を維持するためには、相補的なかたちで両者が共存する戦略が求められている。オンラインとオフラインを横断し、複数のプラットフォームを使い分けることで、批評家は信頼と期待を積み重ね、社会的な影響力を築いていく。
批評の信頼はどこから生まれるのか?
批評の信頼は、作品や論考を通じて構築される長期的なプロセスであり、一過性の情報発信では得られない。また、いまや批評の影響力とは、専門性の高い一撃必殺の論考よりも、継続的な発信を通じた信頼性に置き換わっている。さらに、活動を一人で閉じず、コレクティブやコラボレーションを通じて開かれた場をつくることの重要性も増している。
現在の批評的活動を見渡すと、そこで活躍するのは、複数の形式やメディアに柔軟に対応し、自らの知識や技術を他者との協働に開いていける「オールラウンダー型」の人材である。彼らは、作品分析と社会的語りの双方に強く、かつ迅速に成果を生み出せるスピード感を持っている。これは批評に求められる技術的な要件が厳しさを増していることを意味している。
注目されている批評家の活動に求められる速度と量は増しており、それに伴って消費される速度も加速している。
読まれない時代に、読むに値する批評とは?
この状況では、AIの支援は不可避となるだろう。ただし、AIによる自動整理や要約が日常化した今、私たちは文章を「読む」ことから遠ざかり、「読み飛ばす」ことを前提とした情報摂取が習慣になるだろう。AIが与えてくれる「答え」を、真剣に読み込む時間すら減少している。ここについては改めて検討していくことが必要だろう。
しかし、そうした流れとは裏腹に、美術批評の本質的な価値は今なお生きている。なぜなら、美術作品の意味や意義を社会的に保証するには、専門的な知識と技術をもって書かれた批評が必要だからだ。現代美術の輸出入においても重要な役割を担っている。しかし、近現代美術のフィールドはあまりに広範で、研究者だけではすべてをカバーできない。その隙間を埋めるのが、批評家の役割である。このような人材の育成は、大きな課題になっている。これは、単に広く読まれることとは別の価値系列に属している。
高度な知性とやさしい語り
とはいえ、批評がいたずらに専門用語の多用して、ある種の格式を作り出してもそこで閉じてしまっては、批評のアクチュアリティは縮小していくほかない。近年では、高い教養に裏打ちされながらも、柔らかく開かれた語りができる批評家が、SNS、YouTube、Podcastなどを通じて多くの支持を得ている。
「わかりやすく語ること」は、決して「浅く語ること」とは違う。入門的な態度が、クリシェとして空洞化するのではなく、新たな読者層に向けて再構築されており、批評は再び社会的意義を獲得しうることが示されている。さらに美術館やギャラリーで開催される展覧会や作品を深く理解するため、場合によっては議論を生み出すために批評は、もっと積極的に書かれて良い。美術が持っているアクチュアリティは必ずしも美術を専門とする人々だけに役立つものではなくなっているからだ。
いずれにせよ、活動の形は一つではない。批評活動は、方法論的多元性を持った時代になっている。どう書くか、どのように活動するか、どのような生産性を作り出すかは、各個人が意識して構築していく必要がある時代になった。
石川卓磨
いしかわ・たくま 1979年千葉県生まれ。美術家、美術批評。芸術・文化の批評、教育、製作などを行う研究組織「蜘蛛と箒」主宰。
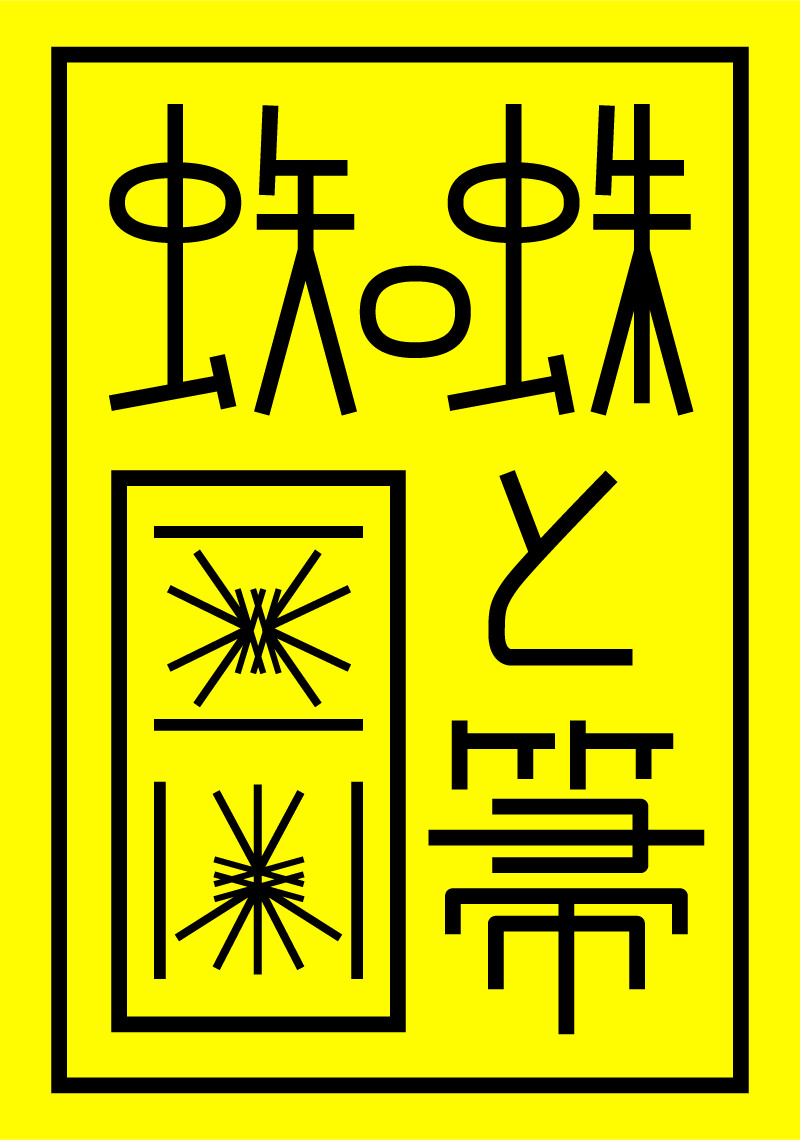
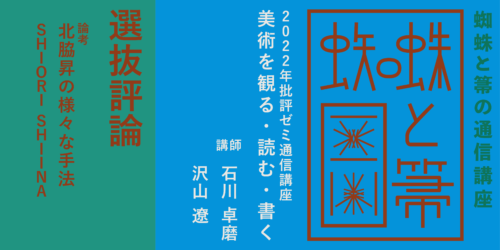
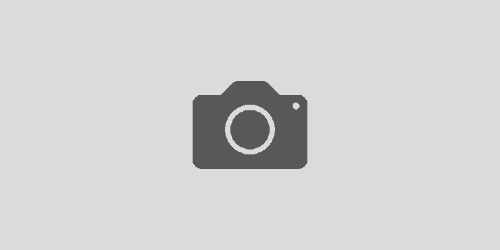
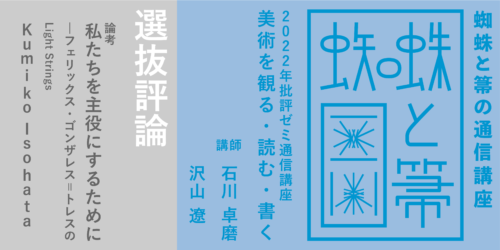
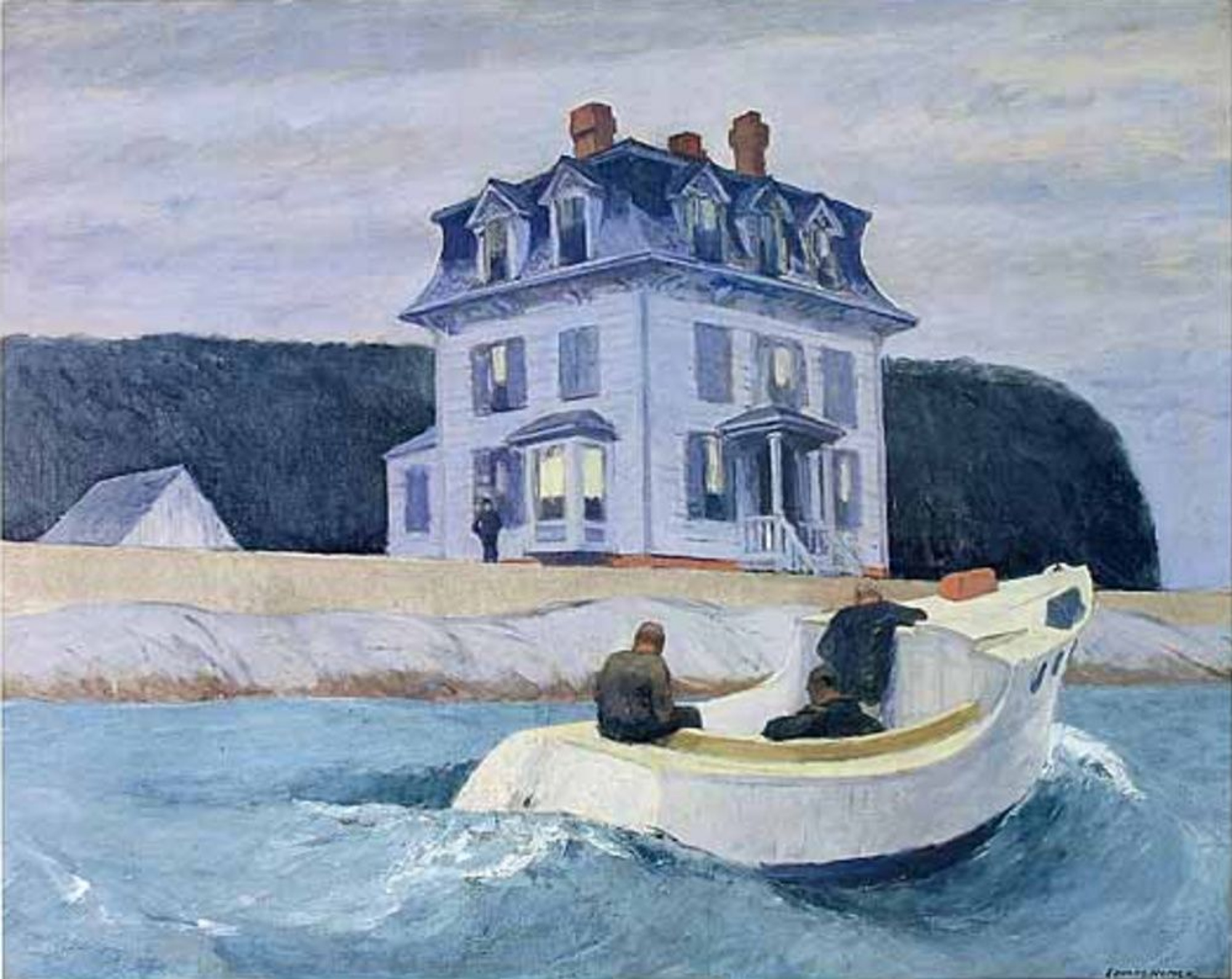

追記:「天気予報は、視覚的に複雑な気象データをいかに理解しやすく伝えるかという課題のもと、常にCG・AR・データ可視化・AI・VRといった先端技術と関わってきた分野である。その意味で、放送における実験的メディア表現のフロンティアであり続けている。」
批評も同様の「技術の実験場」でありたい。
つまり批評というコンテンツのみを目的にするのでは無く、批評が作られる方法の実践自体にも価値があると思っている。そこで培われた経験値は、汎用性を伴って他の領域で役立つ。