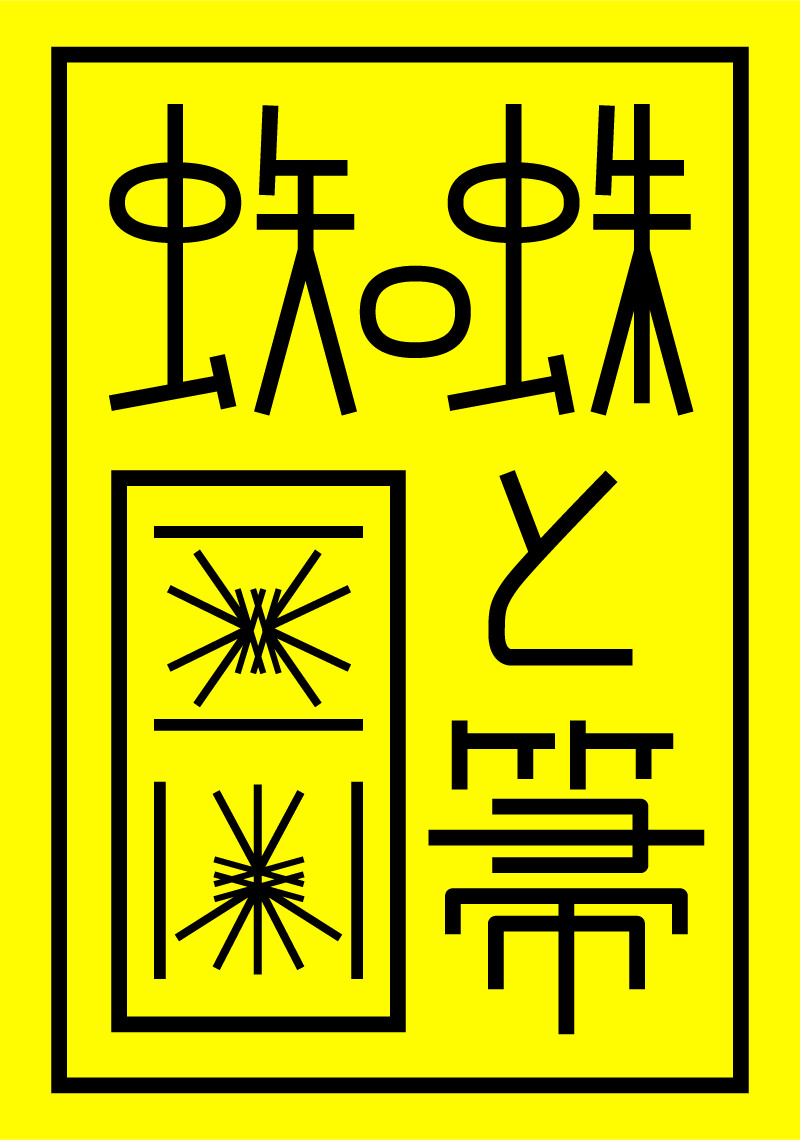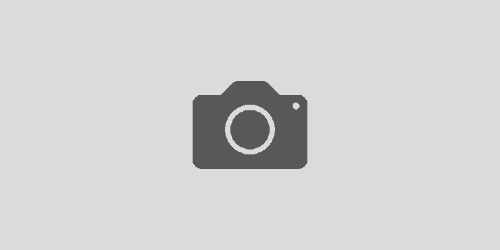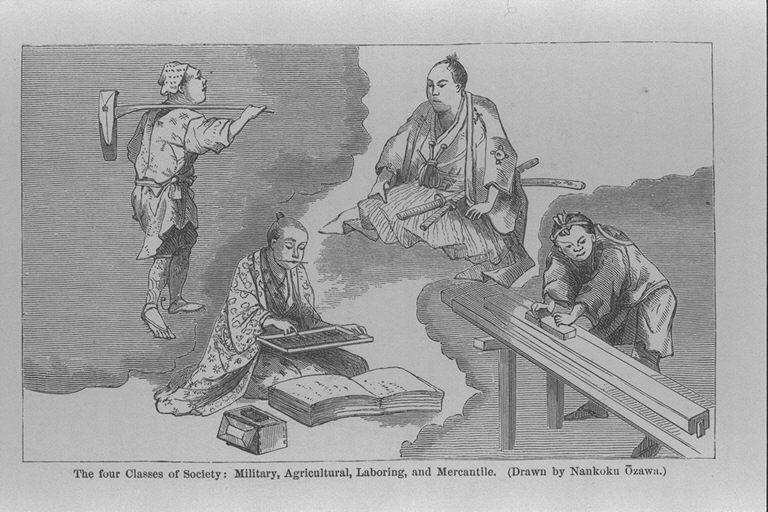ゆがむ現実と映画の正しさ——『スポットライト 世紀のスクープ』
トム・マッカーシー監督『スポットライト 世紀のスクープ』(2015)は、米国の新聞社『ボストン・グローブ』での「スポットライト」という特集記事の記者たちを主人公にした物語である。「スポットライト」の記者たちは、カトリック教会のなかで行われていた性的虐待の事実を知り、その真実を報じるために調査を続けていく。調査を進めていくうちに、性的虐待を行った枢機卿の数は、予想をはるかに超えて多いことがわかった。そして、この一人の枢機卿にとどまらない数多くの枢機卿による多くの性的虐待の実態を、枢機卿たちや彼らの弁護士たちだけでなく、実は『ボストン・グローブ』の記者も知っていたことがわかっていく。ここで問われるのは、犯罪を犯した者とそれを隠蔽していた者たちだけでなく、情報が集まっていたにも関わらず何もしなかった者にも向けられる。この映画では、この事実を報道しなかった記者に強い批判を差し向けることはない。ただし、10年近く前にその事実を報道していれば、性被害者となる児童の数はずっと抑制できたはずである。この事実を本作はしっかりと提示している。2002年の初めに「スポットライト」での報道が行われたことにより、被害者からの報告が相次ぎ、最終的にボストンだけで249人の枢機卿が性的虐待で告発された。被害者の数は1000人を超えることがわかり、200を超える都市で同じような性的虐待があったことがわかった。
これは、MeTooと同じように権力構造が作り出した性暴力とその隠蔽の実態である。また相撲協会のスキャンダルにも同質の問題が孕まれている。その社会を成立させている権力構造、長い歴史を持ちこれからも存続し続けると信じられている組織、人々を救済もしてきた巨大な権力の信用が大きく揺さぶられるとき、人々は不安や不満を感じるはずである。
しかし、暴力の事実は消すことができない。ゆえに、これは然るべきタイミングで自浄を行わなければならない事柄である。変えられるときに変えられなければ全ては泣き寝入りに終わり、人々はますますそれを変えようとしなくなるように思う。このタイプの変化は迅速に成果を出さねばならない。
なぜなら、これは終わりのない戦いでもあると言えるからだ。教会にせよ、映画にせよ、相撲にせよ、全体を破壊し尽くすには、あまりに大きな社会的価値のあるものだ。全てを破壊すればそれで解決よいうことにはならない。そして、人間の欲望、暴力、権力というものも消えるものではない。
2002年に「スポットライト」は、教会側の性犯罪に関する記事を600本掲載したと書いている。これを読んだ人々の苦痛は想像に難くない。だが、映画はそういった終わらなさや社会全体にかかるストレスを消去してきれいに終わる。これが良いことなのか悪いことなのか、判断は複数あるかもしれないけれど、「スポットライト」が行なった報道の正しさは疑い得ないものであり、それを証明して終わる映画の重要性を僕は近年特に強く感じている。観客は、2時間の完結性によって映画を見終わった後にそれを忘れるのではなく、このポイントを揺らがない事実として証明されていることを、心に留める必要があるからだ。
なお、本作は第88回アカデミー賞では作品賞、監督賞、助演男優賞 (ラファロ)、助演女優賞 (マクアダムス)、脚本賞、編集賞の6部門にノミネートされ、作品賞と脚本賞を受賞している。